
はじめに ~体験の場づくりのSTORY~
2003年に廃校となった上田小学校の木造校舎を拠点に、地域ぐるみで都市農村交流活動を開始し、施設の管理運営・活用を行ってきました。地域のあたたかい支援の元、農地や山林をふるさと体験や環境教育と交流のフィールドとして提供いただきながら活動を続けてきました。
2010年からは、施設に隣接する人が立ち入らなくなった山林を借り、ボランティア活動で里山として再生する「ほしはらの森づくり」がスタートしました。2018年には整備してきた山林約1haを取得し、森づくり活動を行いながら、森あそびや自然体験プログラムなどの活動の場として活用しています。
その間にも、次第に周辺農地や景観の維持が高齢化により困難になり、施設隣の水田も休耕となりました。農村景観や生きもの環境への影響が懸念されることから、2021年に水田約1㏊を当法人が無償で借り受け、ボランティアスタッフで草刈り等の管理を行い、一部は畑として利用を始めました。
するとその場所でキジの親子やカヤネズミ、ヤマアカガエル・ニホンアカガエル、アキサンショウウオなどの多様な生物が生息していることが分かり、森と一体的に「里山の生きもの体験ができる環境教育の場」として保全・活用してはどうかというアイデアが生まれました。
そこで、2023年に地域住民と当法人で、100年先もいきもの豊かな里山林、草原、水辺などが織りなす美しい里山の景色が、それを育んできた人々の暮らしとともに維持され、ふるさと自然体験の場として活用されていることを目指して「里山保全活用ビジョン」を策定しました。
現在、専門家によるフィールドの生物や植生の調査を行いながら、様々な課題に対し参加型でひとつひとつ楽しく取り組んでいます。また連携団体や支援団体などたくさんの応援の中、環境整備や管理に関わる人材の育成、環境教育プログラムを実施しています。


体験の場づくりのために行っていること
フィールド活用
自然観察やキャンプなど自然体験活動の場としての活用、また間伐材を薪や炭・クラフトの材料にしたり、原木しいたけを育てたりしながら里山資源の活用を行っています。
.jpg)
.jpg)
フィールド整備
自然体験活動や里山の多様な生き物とふれあえる場(フィールド)づくりを進めるため、ほしはら山のがっこう周辺の森(森林エリア)や草原(休耕田エリア)において、年間を通して草刈りや間伐、水路や観察道の整備などの作業を行っています。
フィールド調査
2023年度から専門家(広島県環境保健協会)に委託し、ほしはら山のがっこう周辺の体験フィールド(ほしはらの森や星の原っぱ)において、植物(植生)や生物(生息)、その他必要な調査を実施しています。
2024年度には、地元上田町の方々に昔の暮らし、地域行事といった地域の様子や、里山の草花や生き物について聞き取り調査を行いました。
.jpeg)
.jpg)
人づくり
フィールド整備活動のリーダー的な役割を担う人材や、里山体験や自然観察などの活動において「ふるさと」を未来につなぐ感性や視点をつなぐガイド人材の育成を行っています。
ご支援・ご協力
里山は、人の手が入ってこそ多様な自然を楽しめる場所に育っていきます。みなさんの「ふるさと」にもなるように一緒に育んでいきませんか?
.png)
★ほしはら山のがっこう里山保全活用ビジョン

上田町の豊かな自然と人々の暮らしが育んできた「ふるさと」は、人間が自然に働きかけ、恵みを得る相互作用の中で長い年月をかけてできあがったものです。一方で、近年、自然と人との関わりが薄れ、このままでは「ふるさと」が失われてしまう懸念も生じています。そこで、今後のほしはら山のがっこうの方向性を明確にするため、ほしはら山のがっこう里山保全活用ビジョンを策定しました。ほしはら山のがっこうが地域と一体となって行う取組により、上田町の自然と暮らし、人々のにぎわいが永続することを目指します。



.png)
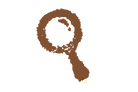.png)
.png)
.png)


